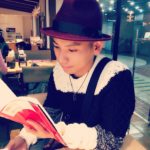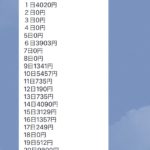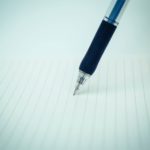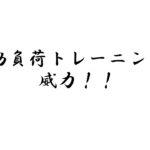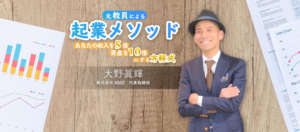2020/09/07
教育の世界でも、子どもたち、保護者のニーズではなく、ウォンツを満たしてあげることはとても大切だ。
ニーズとは、相手の要望。これはヒアリングすれば理解できる。
一方、ウォンツとは、相手が言葉には出さないが、無意識に求めている欲求。
関連記事:満足を超える感動 ~ニーズを満たすだけではリピーターとならない~
ニーズもウォンツも満たし、相手の期待感を遥かに上回る感動を与える。
与え続ける。
それができた時に、ドラマが起きる。
■■■
1.声が出ない・・・
小学校の教員をしていた時、ある女の子を担任した。
5年生のBさん。
大人しくて、どこか周りをキョロキョロと警戒している雰囲気だった。
しかし、時折笑った顔がとっても素敵だった。
Bさんを担任すると分かった時に、前学年の担任の先生から引き続ぎでこんな話が出た。
「Bさんはね、なかなか人前で話すことができないの。発表しようとすると泣き出してしまうの。」
この光景を、私も出会って2日目で見ることになった。
この日は、新しいクラスをスタートしたばかりということで、一人ひとり自己紹介を行っていた。
Bさんの番になる。
その場に立ち上がったはいいが、声が出ない。
しばらく沈黙が続く。
ついに、Bさんはしくしくと泣き出してしまった。
そんなスタートだったが、4月の後半。
家庭訪問を行った。
そこで、Bさんのお母さんの要望を聞くことになる。
「先生、うちの娘は家ではすっごく話すんですよ。今日、学校でこんなことがあった。先生がこんなことしてくれた。って何でも話してくれるんですよ。家では、先生が面白いって話題で4月は持ちきりでした。」
とりあえず、第一関門クリア。
Bさんは、私のことを信頼してくれていることが分かった。
お母さんが話を続けてくれた。
「でもね、やっぱり娘には、学校でもきちんと発表できるようになってほしいんです。」
この言葉が私の心に刺さった。
お母さんも、Bさんが学校で発表できないことを知っていたし、発表できるようになってほしいと望んでいた。
そして、Bさん自身も発表できるようになることを、目標としていた。
つまり、Bさんのニーズも、Bさんのお母さんのニーズも、「発表ができるようになること」だった。
それをサポートし、実現に向けて背中を押すのが私に与えられた使命だ、そんな風に決意を固めた。
2.小さな成功体験の積み重ね
いくつか、策を立てた。
(この策は、以前私がTOSSという教育団体で学んでいた方法を多く取り入れています。)
まずは、授業中声を全員で出す取り組みだ。
授業の中に、必ず声に出して読む時間を設けた。
例えば、国語の時間。
毎時間最初の5分間は、詩や俳句、名文を読み上げて暗唱する時間とした。
子どもたちは意外と、暗唱が大好きだ。
大きな声を張り上げて国語の授業がスタートしていた。
次に、クラス全員に一日一回は、発言する機会を設けた。
私の授業スタイルは次のような形をとった。
質問「1+2はいくつですか。A君。」(誰かをあてる)
子ども「3です」
この質問、応答形式で必ずどの子も一日一回は答えてもらうようにした。
Bさんにも一日一回は、当てるようにした。
ただ、最大限注意をはらった。
絶対に応えられる質問をすること。(簡単な質問)
短い言葉で答えられる質問をすること。
もし、ここで難しい質問をBさんにして、答えられなかったら、今後Bさんは一切発言できなくなってしまう。
だから、常に細心の注意を払った。
幸いにも、Bさんは授業中の質問に答えることができた。
か細い声ではあったが、きちんと答えることができた。
小さな一歩かもしれないけれど、大事な成功体験だった。
少しずつ、Bさんに短い言葉なら発言できる耐性がついていった。
3.討論形式で発言
教科によっては、ほとんど私が話さない討論形式をとっていた。
社会科などがそうだ。
テーマを決める。調べる。徹底的に討論する。
これが子どもたちに大人気だった。
友達と討論することが楽しかったらしい。
さて、この討論をしていると、Bさんはなかなか自分の考えを発言できない。
でも、彼女はノートに事前に書いたことなら発表できた。
だから、ノートに事前に自分の意見を書き、それを読むことで発表してみよう、と提案した。
すると・・・・
見事に意見が言えるようになったのだ。
泣いてしまうこともなく、きちんと自分の意見をノートを読みながら発表出来た。
これが1学期の終わりのことだった。
4.ウォンツは何か
Bさんも、Bさんのお母さんもニーズは「発表できるようになる」だった。
でも、ウォンツ、つまり本当に二人が求めている欲求は少し違うと思っていた。
お母さんは、Bさんの家でよく話す様子を知っていた。
だから、お母さんのウォンツは「本当の娘の姿をクラスのみんなにも知ってほしい」だと感じた。
また、Bさん自身はピアノを習っていた。ピアノが大好きだった。
ピアノは自己表現の一つだ。
だから、彼女のウォンツは「私もみんなの前で自分を表現したい。認められたい。」なのでは、と仮定した。
自己表現欲は、自己肯定感があってこそできる。
自分を大事に思えて、なおかつ周りから大事にされていると感じたときに、自己表現ができる。
そのため私は、まず彼女を褒め続けた。
発言できるようになってきたことを個人的に言葉で褒めた。
また、日記のコメントの中で褒めた。
発言ができた日には、お母さんに一筆箋を渡して、お母さんからも褒めてもらえるようにした。
「今日は嬉しいことがありました。Bさん、授業中に発言できたんです。すごい成長です。きっとドキドキしながら勇気を振り絞ったのだと思います。お家でも褒めてあげてください。Bさんの成長を見ていると、感動します。」
そして、クラスのみんなの前で褒めることもあった。
「Bさんは、最近すごく発言できるようになったよね。すごいよね。もともとBさんは優しい子。その優しい子が、発言するという心の強さも身につけようと頑張っている。優しさと強さ、この2つがBさんの魅力になっているよね。」
そんな話をすると、Bさんは顔を赤くしながらも笑ってくれました。
(私は、毎日日直の子をこのように褒めるようにしていました。)
そうやって、少しずつ少しずつ彼女の自己肯定感が高まるようにしていった。
すると、彼女の発言の数もちょっとずつ増えていき、2学期の中盤には、討論で発言するBさんの姿が日常となっていた。
5.副委員長に立候補
そして、時は流れ3学期。
新たにクラスの学級委員長、副学級委員長を決めようと学級活動を行っていた。
学級委員長をまず決める。
そして、副学級委員長を決めるときになる。
すると・・・
Bさんが副学級委員長に立候補してくれたのだ。
「Bちゃん大丈夫!できるよ。」
そんな風に周りの子に声援を受けながら・・。
恥ずかしそうにしながらも、みんなの前に出て決意表明を述べてくれた。
「私は、このクラスの副委員長になって、クラスを良くしたいです。委員長を精一杯サポートしたいです。」
この光景には、心が震えた。
4月頃は、みんなの前で発言できず泣いていたBさんが、今、目の前で副学級委員長に立候補している。
感動した。
この感動をすぐBさんのお母さんに手紙で伝えた。
すると、お母さんもこんな返事のお手紙を書いてくれた。
「先生、Bが副学級引張に立候補するなんて、夢にも思いませんでした。まさに、奇跡です。感動して思わず涙が出てきました。」
6.今度はバンドだ!
ただ、運命は皮肉なもの。
Bさん以外にも副委員長に立候補した子が多く、実際に副学級委員長になることはできなかった。
(私の学級ではどの子も平等。決意表明だけできたら、あとはじゃんけんで当選を決めていた。)
うわあ、せっかくBさんがさらに成長するチャンスが・・・・
でも、ここであることを思い出した。
そうだ、Bさんはピアノができるんだった。
よし。
私は、彼女にあることを提案した。
「Bさん、先生とお楽しみ会でライブしない?先生がギターと歌、Bさんがピアノ。どう?」
自己肯定感が高まりつつある今のBさんならいける。
そう思っていた。
そして、Bさんは、
コクっ
と首を縦に振ってくれた。
顔を真っ赤にしながら、でも可愛らしい笑顔で。。。
ライブは大好評だった。
そして、3月が終わり、彼女の担任である時間は終わった。
ただ、Bさんはその後も、ピアノ発表会に張り切って出演したり、合唱コンクールがある時には、ピアノの奏者に立候補してくれていた。
■■■
私は、BさんとBさんのお母さんのニーズだけではなく、ウォンツを満たそうと奮闘していた。
本当に、心の奥底の欲求を100%満たすことができたのか。
それは、今でもわからない。
ただ、Bさんが日々成長していく様子は、まさにドラマだった。
人は、誰でも可能性があり、成長できる存在。
そんなことをBさんが教えてくれた。
相手のウォンツを満たそうと思った時に奇跡が起こる。
奇跡は、感動の渦をつくる。
いつも人に感動を与える人間でありたい。
そう思わせてくれたBさんに、心から感謝している。